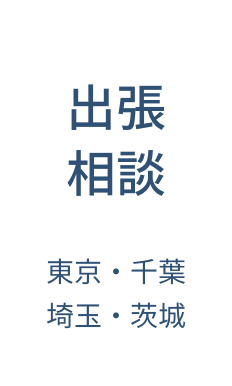

遺言書は「資産家だけが作るもの」「まだ必要ない」と思われがちですが、実は多くのご家庭で役立つものです。遺言があることで、相続手続きがスムーズに進み、大切な人に確実に財産を遺すことができます。
今回は、「遺言があって本当に良かった!」 という実例をもとに、遺言の重要性を解説します。具体的なケースを通して、遺言の効果を理解し、ご自身の相続対策の参考にしていただければ幸いです。
本記事では、遺言書があったことでスムーズに相続が進んだケースを紹介します。司法書士の業務上、実際の事例をそのままお伝えすることはできませんが、守秘義務の観点から個人情報を保護するため、内容をアレンジし、一般的なケースとしてまとめています。
実際の相続の状況により異なる部分もありますが、遺言の大切さを理解する参考になれば幸いです。
【事例】財産の分け方に納得感を持たせたケース
Aさん(80代男性)は、妻と2人の子どもがいる家庭でした。
Aさんの主な財産は、自宅と預貯金3,000万円。
特に自宅は長男夫婦が同居しており、長男は「将来的に自宅を継ぎたい」と考えていました。
一方、二男は独立して遠方で暮らしており、「自分も相続分をしっかり受け取りたい」と思っていました。
そこでAさんは遺言書を作成し、
と明記しました。
【結果】遺言があったことでご家族全員が納得。
長男は「自宅を相続できる」と安心し、二男も「公平な遺産分割」と納得。何より、生前にAさんが「なぜこのように分けるのか」を家族に伝えていたため、遺言書の内容に対する不満はなく、円満に相続が完了しました。
→ 事前にご家族に想いを伝え、その通りの遺言をご準備されたことで、相続人の納得感が高まり、争いを未然に防げたケースです。
【事例】兄弟姉妹との相続トラブルを防いだケース
Bさん(70代男性)は、妻Cさんと二人暮らし。お子様はいらっしゃいませんでした。
Bさんの主な財産は、自宅と預貯金2,500万円でした。
Bさんが亡くなった場合、法律上の相続人は配偶者(Cさん)とBさんの兄弟姉妹です。
Bさんは「すべての財産をCさんに遺したい」と考えていましたが、遺言がなければCさんは遺産の4分の3しか相続できず、残りの4分の1は兄弟姉妹に相続されることになります。
そこで、Bさんは「全財産をCさんに相続させる」 という内容の遺言書を作成しました。
(なお、Cさんも同様に「全財産をBさんに相続させる」という内容の遺言書を作成しました)
【結果】妻が安心して生活を続けられました。
Bさんがお亡くなりになった後、遺言書に従ってCさんが全財産を相続できました。
Cさんは、Bさんの兄弟姉妹と遺産分割協議をすることなく、スムーズに相続手続きが完了しました。
→ お子様のいないご夫婦の場合、遺言がないと配偶者が不利益を被る可能性があります。
確実に財産を配偶者に遺すためには、ご夫婦お互いで遺言を遺すことが大事です。
【事例】法定相続人でない人に財産を遺せたケース
Dさん(60代男性)は、数十年連れ添った内縁の妻Eさんと暮らしていました。
Dさんには前妻との間に子どもFさんがいましたが、交流はほとんどありませんでした。
万が一、Dさんがお亡くなりになると、遺言書がなければ 相続人は実子のFさんのみとなり、Eさんには財産が一切渡らない状況でした。
しかし、Dさんは生前に「Eさんに財産の一部を遺したい」と考え、「自宅と預貯金の一部をEさんに遺贈する」 という遺言書を作成していました。
【結果】遺言のおかげで、内縁の妻が住み続けられました。
Dさんの死後、遺言書があったことでEさんは自宅を遺贈され、そのまま住み続けることができました。遺言には、Dさんが遺言を書いた気持ちや経緯も記されていたため、FさんにDさんの想いも伝わり、Eさんとトラブルにはなりませんでした。
→ 法律上の相続人でない人に財産を遺したい場合、遺言が不可欠です。
今回紹介したケースのように、遺言書があったことで「家族間の争いを防げた」「大切な人に財産を遺せた」 という実例は数多くあります。
遺言書を作成することは、「自分が亡くなった後の家族や大切にしたい方への思いやり」 です。
相続トラブルを未然に防ぐだけでなく、大切な人の生活を守るためにも、ぜひご紹介した3つの事例に近しい境遇の方は、遺言書の作成を検討してみてください。
司法書士は、遺言書作成のアドバイスから実際の遺言執行までサポートできます。
「自分の場合はどうしたらいいのか」と迷われたら、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。
遺言作成についてお考えの方は、弊所へお気軽にご相談ください。
ご相談者様のご意向を大切にし、最適な遺言作成を全力でサポートいたします。